|
| 国際協働プロジェクト |
| 「防災世界子ども会議2005」 |
| "Natural
Disaster Youth Summit(NDYS)2005"
|
防災世界子ども会議2005(Natural
Disaster Youth Summit 2005 NDYS2005)は、阪神・淡路大震災10年を機に、被災地兵庫より誕生したアイアーン*の「防災プロジェクト」である。阪神・淡路大震災で経験した多くの教訓を活かし、兵庫を核とした世界中の子どもたちが、インターネットなど、ICT(情報通信技術)を活用し、国境も言語も宗教も超えて、協働しながら、命の尊さを考えることによって、「防災」の未来について考える国際協働プロジェクトである。
世界中の子どもたちが、命の大切さや人間としての在り方生き方を考え、「世界」に思いをはせることのできる国際的な視野の防災意識を持った子どもを育成することを最大の目的とする。
2004年9月にプロジェクトをスタートさせ、インターネットをつかって、テレビ会議、フォーラムでの交流とディスカッション、ホームページでの活動報告など、子どもたちが大震災の教訓を収集・共有・分析・発信する。
そのまとめとして、2005年3月、世界11カ国から子ども達の代表を迎え、日本の子ども達ともに、「防災世界子ども会議2005
in ひょうご」国際会議をもち、最終日、宣言文を採択し、世界へ発信する。
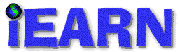
*アイアーン iEARN(International
Education and Resource Network)は、冷戦時代の1988年、「戦争でお互いが傷つけることがないよう、両国の学校間をオンラインで結び、子どもたちと教師が国際協働プロジェクトに取り組むことで、相互理解を深めて欲しいという平和の願いから、ニューヨークとモスクワをつないだプロジェクトを実施したことから始まった。今では、世界約110カ国・2万校・100万人の子どもたちが参加する世界最大級の教育NPOに成長している。ICTを活用し、地球規模のネットワークを通して、環境問題、社会問題、人権問題などをテーマにした国際協働プロジェクトが158も展開されている。iEARNの日本センターが、NPO法人グローバルプロジェクト推進機構JEARN(ジェイアーン)である。
|
テ
ー マ:
大震災の教訓を未来へ 命の尊さを考えよう!
期 間:
2004年9月1日―2005年3月28日
後 援: 兵庫県教育委員会
参加対象: 小学校・中学校・高等学校
参加校:
世界15カ国、国内23校、海外31校、計54校、1,000名以上の生徒が参加
兵庫からは600名以上の生徒が参加
NDYS2005ネットワーク:

使用言語: 英語(共通語)・各国の母語
国際協働学習のツールとしてのICT(情報通信技術)の活用:
|
インターネットなどのICTは、新しい学びの場を生み出す契機を作り出しつつある。本プロジェクトでは、グローバルな新たな防災教育に必要な情報や知恵を、収集、発信、共有することが重要となる。その実現のために、子どもたち、教師の異文化コラボレーションを支えるツールとして、兵庫教育情報ネットワークを活用したテレビ会議、アイアーンのフォーラム、JEARNのML、BBS、BLOGなどICTを駆使し、実施し、その成果を報告する。
|
■ プロジェクトの背景:
1. 防災教育の必要性
・
世界では、自然災害が多発している。大きな被害を受けるのは災害発生地の住民である。しかし、災害前に対策を施す(予防防災)という意識が欠如しているのが現実であり、これは世界的に大きな防災の問題である。この問題を解決する一つの方法は、子どもを対象とした防災教育である。子どもへの教育は、現在及び大人になったときに適切な災害対策を実施できるようになる。
・
兵庫では阪神・淡路大震災以降、命の大切さ・助け合いのすばらしさなど、共生社会における人間としての在り方・生き方を、大震災の教訓に学ぶ「新たな防災教育」として推進してきている。その兵庫から、同じ趣旨で、アイアーン「防災世界子ども会議2005」プロジェクトとして企画し、ネットワークを活用した国際協働学習として展開するものである。
・
2005年1月、21世紀の新しい防災指針とすることとし、災害による被害の軽減を目指す目的で「国連防災世界会議」が兵庫で開催された。環境、平和、人権などの地球規模の諸問題は、一国のみで解決できるものではなく、国際社会全体が一致して取り組むべき問題である。人類共通の課題である「持続可能な開発」の実現に向けて、ユネスコを中心に「国連持続可能な開発のための教育の10年」が推進され、2005年はその最初の年である。本プロジェクトにおける「防災教育」とは、一般に言われる防災教育だけでなく、環境教育、文化教育など多方面に渡っている。
2. 国際教育の必要性
|
国際化が一層進展している社会では、これまでの異文化を理解するだけにとどまらず、子どもたちが国際社会の一員としてどのように生きていくかを考え、行動に移すことが重要となる。
インターネットなどのICTを、国際教育に積極的に活用していくこと が大切である。インターネットが普及して、メールやフォーラムをつかって、世界の教師・生徒と簡単に異文化コミユニケーションができるようになり、さらにブロードバンド化で、テレビ会議を使って世界の教室と異文化コラボレーションができる環境が 整ってきている。国際交流を通じた学習を進める国際協働学習は、英語を共通語として、明確な目標と計画をもち、異文化の人々と深い絆で結ばれることを通して、地球市民(国際社会の一員)であるという意識を育成することにある。
国際化が進行し、種々の問題が国内だけでは解決できない状況であり、国際的視野を持ち、国際社会を生きる人材が必要とされている。そのためにも、国際協働学習は重要である。
|
教材:
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行
「阪神・淡路大震災 教訓集」
兵庫県教育委員会発行 防災教育副読本
「明日に生きる」
■ 防災世界子ども会議
(NDYS) 2005
URL http://ndys.jearn.jp/

■
活動:
参加校の生徒はチームを組み、5つのトピックスの中から自分たちの興味関心にあったものを選び、参加する。今年度は阪神・淡路大震災の10周年にあたり、主に地震についてのトピックスが取り上げられた。その5つのトピックスは以下である。
1.
What are natural
disasters? 災害って何?:過去に発生した地震について調べる(地震の多発地域、地震による二次災害、余震、地震火災、津波、地震の揺れと被害の大きさ)
2.
Why
do they happen? 災害ってどうして起こるの?:災害発生のメカニズムを調べる(地球の仕組み、地震の種類、活断層、地震の予知)
3.
What
can I do? 災害が起こってどうなった?:被災地の被害状況を調べる(人的被害、建築的被害、ライフラインの被害、避難所、仮設住宅、非難時の非常食、被災地での情報ネットワーク)
4.
What
shall we do tomorrow? 災害から身を守るためにはどうしたらいいの?:被害を少なくする防災力について考える(災害への準備と心構え、防災マップの作成、住まいの安全性、応急処置、防災訓練、ボランティア、住みよい街づくり)
5.
How
can I help you? 災害から世界の仲間を助けるにはどうしたらいいの?:命の大切さ、人間としてのあり方、生き方を考え、私たちにできることを考える。(音楽、絵画、住みよい社会作り、支援の輪)
| 〜2004年9月 |
プロジェクト参加校登録 |
| 9月1日〜 |
プロジェクトをスタートする。
同じトピックスを選んだ他校参加者とトピックス毎に分けられたフォーラム(BBS)、テレビ会議で交流しながら学習を進める。
11月〜12月
各学校の成果物を完成させ、ウェブ上で公開する。テレビ会議で交流しながら学習をすすめる。 |
|
|
| 2005年1月 |
淡路島国営明石海峡公園「春一番の丘」で河津さくら記念植樹
プロジェクトの中間発表として、阪神・淡路大震災10周年記念事業、国連防災世界会議
パブリックフォーラム「復興への思いが世界を包む 絵画展・写真展とテレビ会議」を兵庫県立淡路夢舞台国際会議場で開催する。
会議の様子は、テレビ会議で参加校をつなぎ、インターネットを通じて兵庫より、世界中にライブ配信する。 |
| 2005年2月 |
プロジェクトのまとめとしての3月開催の国際会議に向け、発表の練習をする。同時に、他校の成果物に対しての感想をフォーラムで述べあう。 |
| 3月25日〜28日 |
阪神・淡路大震災10周年記念事業
「防災世界子ども会議2005
inひょうご」国際会議
国際会議に各学校から参加し、プレゼンテーション、ポスターセッションなどで報告する。最終日、「防災世界子ども会議2005-ひょうご宣言-」を採択し、世界に向けて発信する。
|
| 6月28日 |
プロジェクトの最終報告書の発行 |
■ 国際協働学習のツール
1)
テレビ会議
未来を支える子どもたちのために、全国の最大級の情報通信ネットワークを誇る兵庫教育情報ネットワークを活用し、ひょうごeースクール構想の一環として、インターネットによるテレビ会議を活用して、「防災について知りたい、学びたい、伝えたい」ことを、海外の生徒との交流を通して、情報交換を行う。
|
|

|
2004年9月1日
9月1日は防災の日
この日「防災世界子ども会議プロジェクト」がスタート!
兵庫県明石市立野々池中学校の生徒会のみなさんが、アイアーンエジプト・ユースサミット会場と兵庫県教育研修所を結んだテレビ会議を行った。
|
|
|
|
 |
2004年10月22日
台湾、イランとのテレビ会議 |
|
|
|

|
2004年12月3日
6カ国、11ポイントを結ぶテレビ会議 |
|
|
|
 |
2005年1月18日
「復興への思いが世界を包む
絵画展・写真展とテレビ会議」
「防災世界子ども会議2005
inひょうご」国際会議の中間発表
イラン大震災支援プログラム 「書き損じはがきプログラム」報告 兵庫県香呂南小学校
書き損じはがきを集めて2003年12月に発生したバムの義捐金に変えた活動を報告した。暗記した英語で、撮影カメラに手を振ると、バムの子ども達から、笑顔のメッセージが返ってきた。
|
|
 |
|
|
|
 |
防災ポストベアの冒険
NDYSプロジェクトを通して交流のある世界の学校へ、防災ポストベアが「こころのケア」郵便を届けている。名古屋市立柳小学校の6年生は、交流のあるスロバキアの子どもたちへ、クリスマスプレゼントのお礼を、夢舞台会場とつないだテレビ会議で実現した。
ロシア、セネガル、アルゼンチンの学校とも「こころのケア」を通して交流を続けていく。
|
2) マテリアル
|
参加校の教師が、それぞれに提供した素材を、共有しているページである。フォーラム、メール、テレビ会議と交流を重ねることで、アイアーンNDYSコミユニティが誕生した。 |

マテリアル
URL: http://ndys.jearn.jp/2005/material.html
|
■ 生徒、教師の声
3月25日〜28日の全体会議中に、参加している生徒及び教師に対して、NDYS2005についてアンケート調査を行った。以下は、生徒、教師からの意見の一部である。
生徒へのアンケート
●NDYSで興味深かったこと
・
自然災害の知識を共有できたこと
・
プレゼンテーションをつくる、見る
・
グループでの作業
・
たくさんの友達ができた
・
他の国の習慣や伝統を知ることができた
地震が懸念される地域なので、地震の情報を得ることに興味をもった
●学校での行動の変化
・
クラスメートに地震について教えている
・
他の生徒がNDYSを知るようになって、国際的なニュースに気を配るようになった
・
以前より興味を持つようになったので、学校で広めようと思う
・
世界で被害にあった人を助けるために、友達に話をしようと思う。
・
いろいろな知識を得て、それをすべての生徒で共有した
・
自然災害について友達に話そうと思う
NDYSについて友達に話した
●家族に対する行動の変化
・
お互いを大事にする
・
家族にたくさんのことを伝えられるようになった
・
近所の人と連携できるように、家族に話をしようと思う
・
自然災害のこと、災害中にするべきことを話そうと思う
自然災害について話したいと思うようになった
●コミュニティに対する行動の変化
・
社交的になった
・
リーダーになりたい
・
コミュニティに対して災害対策を教えようと思う
・
コミュニティの意識を高め、対策をしてもらうようにする
・
自然災害について教えることができる
変化はない
●次回のNDYSでしたいこと
・
世界の飢餓について学びたい
・
自然災害に対する活動をもっと学びたい
・
地震についてさらに学びたい
・
ディスカッション
自分の国では発生しない自然災害について学びたい
教師へのアンケート
●生徒が興味を持っていた内容
・
プレゼンテーション
・
ディスカッション
・
たくさんの国の習慣や伝統
災害の研究
●次回のNDYSに必要な内容
・
内容は今のままでよい
・
すべてのレポートをまとめるオンラインフォーラム
・
安全な村、安全な都市、安全な大都市をつくることを考える
時間、日数
●生徒の行動の変化
・
新しい世界観を持つようになった
・
自然災害を意識するようになった
・
他人に対してオープンになった
・
異なる国の人と異なる言語でコミュニケーションできるようになった
・
地震リスクマネジメントに関わることをするという新しい考えを持つようになった
・ ディスカッションすることにより、多くの情報と経験を得て、考え方が大きく変わった
環境問題に意識を持つようになり、より良い世界を作るべきだという考えを持つようになった。
|
NDYS2006へ
back
|